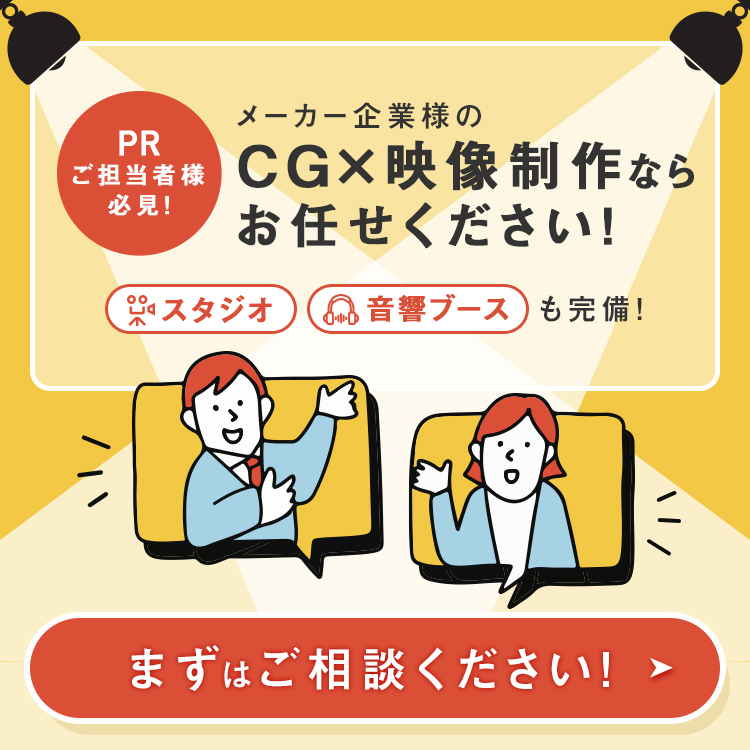企業が自社商品・サービスなどをアピールできる展示会は、潜在顧客となりえる来場者が多く集まるため、絶好のビジネスチャンスです。来場者に興味を持ってもらい、商品・サービスを理解してもらう必要があり、動きのある動画を活用すれば、文字や写真だけの説明よりも認知・理解を高めたり、興味関心を高めたりすることができます。
この記事は、展示会動画の重要性から効果的な制作方法、活用事例、費用相場、最新トレンドまで、展示会動画に関するあらゆる情報について解説します。これから展示会動画を導入したい方や、既存の動画活用をさらに進化させたい方にとって、実践的なヒントとノウハウを提供します。
展示会動画とは?注目される理由と活用の重要性

近年、展示会における動画活用が急速に広がっています。その背景には、来場者の注目を集めやすく、短時間で多くの情報を伝えられるという動画ならではの特性があります。また、動画は視覚と聴覚の両方に訴えかけるため、商品やサービスの魅力をよりリアルに伝えることが可能です。
展示会場の限られたスペースや時間の中で、効率的に自社の強みをアピールできる手段として、動画は今や欠かせない存在となっています。また、展示会終了後もWebサイトやSNS、営業資料などに二次利用できるため、費用対効果が高い点も魅力です。
動画は単なる「展示ブースの演出」ではなく、ブランディングや販促活動を支える重要なコミュニケーションツールとなっています。さらに、オンライン展示会やバーチャルイベントの普及により、動画の重要性はますます高まっています。
展示会における動画活用のメリット
展示会で動画を活用する最大のメリットは、来場者の目を引き、足を止めてもらえることです。動きや音、インパクトのある映像表現によって、静止画やパネルだけでは伝えきれない情報や魅力をダイナミックに伝えることができます。また、複雑な製品やサービスの仕組みも、動画なら分かりやすく解説でき、理解促進や興味喚起につながります。
映像演出によって企業の世界観や技術力を印象的に伝えられるため、他社との差別化にも有効です。また、海外向け展示会では言語を超えたコミュニケーションツールとして機能し、来場者との接点を拡大します。さらに、スタッフが説明できないタイミングでも動画が自動で情報提供してくれるため、ブース運営の効率化にも貢献します。
来場者・営業活動への効果とは?
展示会動画は、来場者の「足を止める力」と「営業後の記憶定着力」を高めます。ブース前を通る人の視線を映像が引きつけ、興味喚起のきっかけを作ります。そして動画で概要を理解した来場者に具体的な質問や商談が発生しやすくなり、営業担当者の説明負担も軽減します。その結果、来場者の理解度や購買意欲が高まりやすくなります。
また動画を活用することでオンライン配信も可能となるので、ブースに立ち寄った人だけでなく、新たなリード獲得や継続的なタッチポイントが生まれます。営業活動の初期段階で「動画で覚えてもらう」ことで効率的な商談が実現し、後の商談成約率の向上にもつながります。
動画で差別化する意義と目的
多くの企業が出展する展示会では、いかに自社ブースを目立たせ、他社と差別化するかが重要な課題です。動画は、独自の映像表現やストーリー性、インパクトのある演出を取り入れることで、来場者の記憶に残る強力なコンテンツとなります。またブランドイメージの向上や、企業の先進性・信頼性をアピールする手段としても有効です。
動画は単なる情報伝達だけでなく「ブランド体験」を提供します。展示会動画を活用する目的は、“記憶に残る体験価値”を創出することにあります。体験価値や感情に訴える演出を盛り込むことで、競合との差別化を図ることができるのです。
展示会動画を活用したいその他のシーン
展示会動画の活用は会場だけに留まりません。街頭での大型モニターやLEDビジョンでの放映に加え、QRコードを活用してスマホ閲覧を促すなど、来場者自身で動画にアクセスする仕組みも増えています。また、オンライン展示会やハイブリッドイベントでは、同じ映像をWeb配信用に編集して再利用できるため、制作コストを抑えながら広範囲のプロモーションが可能です。
さらに展示会終了後には、SNS投稿やYouTubeチャンネルで再配信し、見逃した潜在顧客にも情報を届けられます。展示会動画は“イベント限定”ではなく、展示会を起点にマーケティング全体を動かすコンテンツとして位置づけるのが効果的です。
展示会動画の最新トレンドと映像表現の進化

展示会動画の表現手法は単なる「紹介映像」から「体験演出」へと進化しています。最新のトレンドを取り入れることで、より高い訴求力と話題性を生み出せます。来場者にブース内で“ブランド体験”を感じてもらうため、映像はより没入感とインパクトを重視した方向へ進んでいます。近年では、LEDビジョンや透明ディスプレイなどの大型映像装置を組み合わせたりと、空間全体で魅せる演出が増えています。
さらに、オンライン配信やSNS活用を前提にしたマルチデバイス対応も必須になっています。展示会動画は、映像表現とデジタル技術の融合によって、ブランドの世界観を体験として伝える重要なコンテンツへと進化しているのです。
テロップ・アニメーション・CGなど最新表現手法
展示会動画では、テロップやアニメーション、CG(特に3DCG)を活用した映像表現が主流となっています。テロップは、音声が聞こえにくい会場でも情報を伝えられるため必須の要素です。アニメーションやCGは、複雑な製品構造やサービスの流れを視覚的に分かりやすく表現でき、来場者の理解を深めます。
また、テロップやキービジュアルをブランドカラーで統一することで、視覚的な印象を強調できます。BGMやサウンドエフェクトも重要な要素で、音の演出によってブース全体の雰囲気をコントロールでき、印象に残る演出が可能です。これらの最新手法を取り入れることで、他社との差別化や話題性が期待できます。
実写×アニメのハイブリッド事例
実写映像とアニメーションを組み合わせたハイブリッド動画は、展示会動画の新たなトレンドです。実写でリアルな現場や製品を見せつつ、アニメーションで補足説明やイメージ表現を加えることで、分かりやすさとインパクトを両立できます。
例えば、実写の工場風景にCGで製品の内部構造を重ねたり、キャラクターアニメでサービスの流れを解説したりする事例が増えています。この手法は、来場者の興味を引きつけ、記憶に残る映像体験を提供します。
また、BtoB商材であっても硬い印象を与えず、ストーリー性を持って紹介できるため、来場者の興味を引きやすいのが特長です。特に新技術や抽象的なサービスを説明する際に有効で、理解を助けるだけでなく、SNSやWeb用にも展開できるのがメリットです。
オンライン展示会・バーチャル活用の活用拡大
コロナ禍以降、オンライン展示会やバーチャルブースが急速に普及し、動画の重要性はさらに高まりました。オンラインでは、来場者が自由に動画を選んで視聴できるため、情報の整理と編集が成果を左右します。また、リアル展示会と組み合わせた「ハイブリッド展示会」では、会場動画をオンライン配信用に再編集して活用するケースも増えています。
3D空間やインタラクティブ動画など、体験型コンテンツとの融合も進んでいます。動画の活用方法も大きく進化しています。360度動画やバーチャルツアー、インタラクティブ動画など、来場者が自宅からでも臨場感を味わえるコンテンツが登場しています。
また、チャットボットやライブ配信と連動した動画活用も進み、リアルタイムでのコミュニケーションや商談が可能になりました。これらにより、物理的な制約を超えた新しい展示会体験が実現しています。展示会動画はリアルとデジタルをつなぐツールとして、今後ますます重要になって来ると考えられます。
映像機器・撮影機材の進歩と展示会ブース演出
映像機器や撮影機材の進化により、展示会動画のクオリティは格段に向上しています。4K/8Kカメラや高性能ドローン、ジンバル、LEDディスプレイなどの最新機材を導入することで、鮮明で迫力ある映像表現が可能になります。
また、タッチパネルや大型モニター、プロジェクションマッピングなど、ブース内での映像演出も多様化しています。これらの機材を効果的に活用することで、来場者に強いインパクトを与え、ブース全体の魅力を高めることができます。映像機器はもはや演出の手段ではなく、ブースデザインと一体化した体験創出の要素となっています。
| 機 材 | 特 徴 |
| 4K/8Kカメラ | 高精細な映像撮影が可能 |
| ドローン | 空撮やダイナミックな映像表現 |
| LEDディスプレイ | 大画面で鮮やかな映像表示 |
AI生成映像・モーションキャプチャの活用事例
AI技術を活用した展示会動画も増えています。生成AIを使ったモーショングラフィックスや、AIナレーションによる多言語対応、モーションキャプチャで人の動きをリアルに再現する映像など、制作コストを抑えつつ高品質な表現が可能になりました。
また、AI分析によって来場者の反応データを収集、改善につなげる企業も登場しています。これにより、動画制作が「一度作って終わり」ではなく、「データを基に進化するコンテンツ」へと変化しています。AI映像技術の導入は、限られた展示時間で最大の効果を引き出す有効な手段です。
効果的な展示会動画の制作ステップと依頼の流れ

展示会動画を成功させるためには、明確な目的設定から企画、撮影、編集、納品までの一連の流れをしっかり押さえることが重要です。短期間で成果を出すためには、制作会社との密な連携がポイントです。まず、「誰に」「何を」「どのように伝えるか」を整理し、それに基づいて映像のトーンや構成を決めます。
次に、スケジュール・撮影計画・納品形式などを事前に明確化することで、当日や納期直前のトラブルを防止できます。展示会は日程が固定されているため、制作工程の効率化が成功の鍵を握ります。制作ステップを理解して臨むことで、訴求力の高い動画をスムーズに完成させることができます。
企画・ヒアリングで決めるべきこと
動画制作の第一歩は、目的やターゲット、コンセプトを明確にすることです。企画段階では、展示会動画の「目的」を具体化することが最も重要です。例えば、「新製品の機能訴求」「企業ブランドの強化」「集客力アップ」など、狙いによって構成や演出が変わります。
ヒアリングでは、ターゲット層(技術職・購買担当・経営層など)や展示会テーマを明確にし、映像のトーンや長さを決めていきます。コンセプトを定めずに制作を進めると、伝えたいメッセージが曖昧になり、印象に残らない映像になりがちです。目的・ターゲット・訴求内容を一貫して整理することで、効果的な映像設計が可能になります。
絵コンテ・構成案・演出アイデアの作り方
企画が固まったら、次に絵コンテや構成案を作成します。絵コンテとは、映像の流れやカット割、演出イメージを視覚的にまとめた設計図のようなもの。構成案では、ナレーションやテロップ、BGMの使い方、アニメーションやCGの挿入ポイントなども具体的に検討します。
また、展示会では「冒頭3秒で注目を集める」ことが重要なため、最初のシーンに強いインパクトを持たせる演出を考えましょう。さらに、音楽や色彩設計などもコンセプトに合わせて選ぶことで、ブランドの一貫性が高まります。構成段階の完成度が、動画全体のクオリティを大きく左右します。
撮影方法・機材・映像制作会社の選び方
撮影方法や使用機材は、動画のクオリティや表現力に大きく影響します。実写・アニメ・CGなど、目的に合った手法を選びましょう。まず確認すべきは撮影スタイルと機材の選定で、製品の質感や動きを魅せる場合は、マクロ撮影やスライダー撮影を用いたダイナミックな映像が効果的です。一方で、企業紹介やインタビューを中心に構成する場合は、照明と音声収録の精度が重要になります。
制作会社を選ぶ際は、展示会動画の実績があるか、企画力と撮影技術の両面を持っているかを確認しましょう。単なる映像制作業者ではなく、「ブース演出」や「マーケティング効果」まで理解しているパートナーを選ぶことで、成果の出る映像が完成します。また、過去の実績や得意分野、対応力、見積り内容を比較検討することが大切です。撮影現場の下見やリハーサルも、トラブル防止やクオリティ向上に役立ちます。
| 選定ポイント | チェック内容 |
| 実 績 | 展示会動画の制作経験 |
| 得意分野 | 実写・アニメ・CGなど |
| 対応力 | 企画~納品までのサポート |
| 見積り | 費用・納期・内容の明確さ |
編集・デザイン・テロップ・BGMのコツ
編集では、動画を「見やすく」「記憶に残る」ものに仕上げる重要な工程で、テンポの良いカット割や、見やすいテロップ、統一感のあるデザインが重要です。不要な情報を削ぎ落とし、伝えたいメッセージを明確に一本化することが大切です。1本の動画内で複数の要素を詰め込みすぎると、来場者の理解が追いつかず、印象が薄れてしまいます。
展示会場では音声が聞こえにくい場合も多いため、テロップやアイコンで情報を補完しましょう。編集段階ではテンポと間の調整が効果を左右します。また、ブランドカラーやロゴの活用、BGMの選定にもこだわることで、印象的な動画に仕上がります。3分以内でテンポよく展開し、最後に印象的なブランドロゴで締める構成が理想的です。編集段階での細かな工夫が、来場者の記憶に残る映像体験を生み出します。
二次利用を前提とした納品と資産化
完成した動画は、展示会場だけでなく、オンライン展示会や自社サイト、SNS、YouTubeなど多様なプラットフォームで活用できます。納品時には、用途に応じて各媒体に最適なファイル形式や画質、字幕対応などを確認しましょう。また、スマホ対応の縦型やスクエア型など短尺版やダイジェスト版を用意することで、さまざまなシーンで活用の幅が広がります。
活用シーンを想定した納品・運用体制を整えることが、動画の効果最大化につながります。展示会終了後も営業ツールやプレゼン資料、Web広告などに再利用できるため、汎用性の高い編集データを保管しておくと便利です。制作段階で「二次利用を前提とした設計」を意識すれば、投資対効果を大きく高めることができます。動画は“一度限りの展示コンテンツ”ではなく、“長く使える営業資産”と考えましょう。
展示会動画の種類と選び方

展示会動画にはさまざまな種類があり、目的やターゲット、伝えたい内容によって最適な形式を選ぶことが重要です。例えば、企業ブランディングを重視する場合と、製品のスペックを訴求する場合では、構成も表現も大きく異なります。効果的に活用するためには、「何を伝えたいか」を明確にし、それに最適なタイプを選ぶことが重要です。以下に代表的な展示会動画の種類と目的を表にしました。用途に応じて使い分けることで、展示会での訴求力が大きく向上します。それぞれの動画タイプの特徴と選び方を理解し、効果的な活用を目指しましょう。
| 種 類 | 主な目的 | 効果・特徴 |
| 企業紹介動画 | ブランド価値の訴求・信頼感の構築 | ストーリー性や理念を伝え、企業イメージを強化 |
| 商品紹介動画 | 製品の機能・特長の理解促進 | CGや実演で分かりやすく機能を説明 |
| デモンストレーション動画 | 実際の使用感・導入効果の提示 | 製品の信頼性を高め、購買意欲を喚起 |
| ティザー/オープニング動画 | 集客・注目喚起 | 会場で足を止めさせるインパクト重視の演出、期待感を演出 |
| ハウツー/チュートリアル動画 | 操作方法・活用事例の説明 | 実用的情報で理解を深める、使いたくなる演出 |
企業紹介・ブランディング向け映像
企業紹介やブランディングを目的とした動画は、会社の歴史や理念、ビジョンなどをストーリー仕立てで伝えるのが特徴です。「どんな会社か」を短時間で印象づけることが重要なため、映像のトーンやナレーションに統一感を持たせることがポイントです。特に製造業では、技術力や製造工程、開発者インタビューなどを交えた映像が効果的です。
歴史や理念を語るだけではなく、「なぜこの会社が選ばれるのか」を具体的に示す構成が求められます。展示会の冒頭やブースのメインスクリーンで流すことで、来場者に企業の信頼感や先進性をアピールでき、商談やリード獲得のきっかけ作りにも役立ちます。展示会後には企業サイトや採用動画として活用できるため、長期的なブランド資産として制作する価値があります。
製品・サービスの紹介動画
製品紹介動画は、展示会動画の中でも最も需要が高いジャンルです。特徴的な機能や他社との差別化ポイントを映像で分かりやすく伝えることで、来場者の理解と関心を高めます。特に製品の内部構造や仕組みを見せる場合には3DCGを活用すると効果的です。
またデータを羅列するよりも、実際の使用シーンや導入事例、スペック比較などを交えて構成すると、来場者の理解と興味を高め印象に残ります。また、アニメーションやCGを活用することで、複雑な機能や仕組みも直感的に伝えられます。
展示会場では、短時間で要点を伝える構成が効果的です。インパクトを与える必要もあるため、「導入メリット」を冒頭に明示する構成が成果につながります。
デモやハウツーを伝える動画
デモ動画やハウツー動画は、製品の使い方や操作手順、導入後の活用方法を具体的に解説する映像です。デモ動画は、業務用機器やソフトウェア製品では、カタログだけでは伝わらない使用感を映像で補完できます。またハウツー動画は、操作性やメンテナンス性を示すことで“使いやすさ”を印象づける効果があります。
展示会では、スタッフの説明を補助する役割を果たすため、シンプルでテンポの良い構成が適しています。音声が聞こえにくい場合も多いため、視覚的な解説やアイコンを用いた説明が有効です。
実際の操作画面や手順を見せることで、来場者が自分で使うイメージを持ちやすくなり、購買意欲の向上につながります。また、FAQやトラブルシューティングを盛り込むことで、展示会後のフォローやサポートにも活用できます。
ティザー・オープニング映像でBGMや字幕を活用
展示会の冒頭で放映されるティザー動画やオープニング映像は、来場者の足を止めさせて興味を引きつけるための短尺動画です。映像の開始3秒でインパクトを与えることがポイントで、動きのあるグラフィックや力強いBGM、印象的なキャッチコピーを活用することで、ブースへの誘導や話題作りに効果的です。
また、展示ブース内のBGMやサウンドデザインを統一することで、ブースの雰囲気やブランドイメージを演出できます。字幕を活用すれば、海外展示会や多言語の来場者にも対応でき、国際的なブランドイメージ向上にもつながります。ティザー動画は“ブースの顔”として、短くても印象に残る演出がポイントです。
成功する展示会動画の活用事例・効果と工夫

展示会動画は、単に流すだけでは成果を最大化できません。成功事例を見ると、動画とブース演出や体験コンテンツを組み合わせることで、来場者の理解と記憶に残る体験を提供しています。動画を活用したブースは来場者の滞在時間が長くなり、営業担当者との接点も増加しています。
情報量が多い製品や複雑なサービスの場合、動画で要点を整理することで来場者の理解度が大幅に向上します。また、展示会終了後も動画を営業資料やWebコンテンツに再利用することで、ROIの向上にも寄与します。
業界別での導入・成功事例の紹介
製造業では、製品の内部構造や動作原理をCGで可視化した動画が注目を集めています。IT・ソフトウェア業界では、サービスの流れや操作デモやUIの動作をアニメーションで分かりやすく示すことで、理解と導入意欲を同時に高める事例が多く見られます。
また、医療・ヘルスケア分野では、製品使用の手順や安全性を実写とCGを組み合わせたハイブリッド映像で信頼性と先進性をアピールするケースが多く見られます。業界ごとに訴求ポイントは異なりますが、共通して言えるのは「製品やサービスの魅力を短時間で分かりやすく伝え、来場者の記憶に残す」ことが成功の鍵です。
| 業 界 | 活用事例 |
| 製造業 | CGで内部構造や動作原理を可視化 |
| IT業界 | アニメーションでサービスやUI動作を説明、操作デモ |
| 医 療 | 使用の手順や安全性を実写×CGのハイブリッド映像 |
展示会ブース設計×映像演出の工夫
成功する展示会では、ブース設計と映像演出が密接に連動しています。大型モニターや壁面投影を効果的に配置し、例えば、ブースの通路側にティザー動画を放映し来場者の足を止めさせ、ブース内部に詳細なデモ動画を放映する二段階の導線を設計するなど、来場者が自然に動画に視線を向けるようになっていることが重要です。また、体験型演出と組み合わせることで、動画を見た後に操作体験や質問を促す流れを作れます。
また、タッチパネルやインタラクティブ映像を取り入れることで、来場者が自ら情報を選択・体験できる仕組みも効果的です。映像と空間デザインの融合が、印象的な展示会体験を生み出します。ブース全体でブランドの世界観を演出する事例が増え、来場者の記憶定着を強化し、競合との差別化につながります。
情報量を最適化する動画の長さ・時間
展示会動画は、来場者の滞在時間や集中力を考慮し、一般的には1〜3分程度の短尺が効果的とされています。短時間で要点を伝えることで、情報過多による離脱を防ぎ、印象に残りやすくなります。
また、複数の短尺動画と長尺動画を用意し、目的やターゲットに応じて使い分けるのも有効です。動画の長さ・情報量を最適化することで、展示会での訴求力が大きく向上します。
来場者参加型コンテンツ・体験型動画の事例
来場者が自ら操作したり体験できる参加型コンテンツは、展示会での注目度が高まっています。タッチパネルで製品情報を選択できる動画や、AR/VRを活用した体験型映像など、インタラクティブな仕掛けは理解度が高まり滞在時間も増加し、来場者の満足度を高めます。
またクイズやアンケートと連動した動画は、来場者の行動データを収集し、後日営業フォローに活用する事例もあります。体験型動画は、単なる映像視聴では得られない「記憶」と「関与」を作ることができるのがメリットで、リード獲得や商談への誘導に効果的です。
展示会動画制作の費用・相場・コスト削減のヒント

展示会動画の制作費用は、内容や尺(長さ)、表現手法などによって大きく異なります。費用相場を把握し、見積りのポイントやコスト削減の工夫を知ることで、予算内で最大限の効果を得ることができます。
また、補助金や助成金の活用、運用方法の工夫によって、コストパフォーマンスを高めることもできます。ここでは、動画制作の費用相場や見積りのポイント、コスト削減のヒントを解説します。
動画制作会社選びと見積りのポイント
動画制作会社を選ぶ際は、実績や得意分野、対応力などを重視しましょう。展示会動画の制作経験がある会社は、ブース演出や来場者心理を理解しているため、効率的かつ効果的な提案が可能です。
見積りでは、企画・撮影・編集・CG制作・ナレーションなど、各工程の費用が明確に記載されているかを確認することが大切です。また、修正回数や納期、追加費用の有無も事前にチェックしておくと安心です。
費用相場・補助金・予算策定の考え方
展示会動画の費用相場は、短尺でシンプルなアニメーション動画で30万円〜100万円程度、実写撮影やCGを多用した本格的な動画では100万円〜300万円程度が一般的な相場です。「事業再構築補助金」や「IT導入補助金」など、自治体や商工会議所の補助金・助成金を活用できる場合もあるため、事前に情報収集しておくと良いでしょう。
予算策定時は、目的や活用シーンに応じて必要なクオリティや尺を見極め、無理のない範囲で最大効果を狙うことが重要です。また制作コストだけでなく、会場設置やオンライン配信のコストも含めて、総合的に予算を策定することが重要です。
| 動画タイプ | 費用相場 |
| シンプルなアニメーション | 30~100万円程度 |
| 実写撮影+CG多用 | 100~300万円程度 |
コスト効率を高める制作・運用ノウハウ
コスト効率を高めるには、汎用性の高い動画を制作することで、複数の用途で使い回せる構成にするのが有効です。また撮影やCG制作をまとめて発注することで工程を効率化し、制作費を抑えることも可能です。さらに過去の映像素材を活用して更新・改変することで、新規制作費を削減できます。
また展示会動画は、短尺版やダイジェスト版を同時に制作し、展示会後のWeb配信、SNS、営業資料、採用活動など、二次利用を前提に設計するとROIが向上します。自社で簡単な編集や字幕追加ができる体制を整え、運用コストの削減も可能です。制作会社と連携し、長期的に使える設計と二次活用を意識することが、コスト削減のポイントです。
展示会動画を成功に導く運用・改善のポイント

展示会動画の導入後は、動画の運用や分析、チーム体制の整備が欠かせません。担当者やチームで役割分担を明確にし、更新・リニューアルしながら改善を重ね、継続的な成果につなげていきます。また、トレンドや新技術にもアンテナを張り、常に最適な動画活用を目指しましょう。
成果を最大化するためのPDCAと効果測定
展示会動画の効果を最大化するためには、事前の目標設定と事後の分析・改善が重要です。来場者の視聴状況や滞在時間、問い合わせ件数、商談数などをデータとして取得し、どの動画が関心を引いたかを評価します。
その上で、次回展示会用に尺や演出、テロップ表示の改善を行うことで、動画の訴求力は継続的に向上します。アンケートやヒアリングも活用して来場者の声を反映させ、効果測定の結果を基にPDCAサイクルを回し、動画内容や活用方法を改善し続けることで、より高い成果を得ることができます。
担当者の役割・チーム連携の体制づくり
展示会動画を効果的に活用するには、担当者やチームで役割分担を明確にし、制作会社との連携体制を整えることが大切です。企画・撮影・編集・ブース運営・営業フォローなど、各工程で担当者が役割を理解して情報共有や進捗管理を徹底することで、スムーズな進行が可能になります。
特にブース設営時の映像セッティングや音声確認、タイムスケジュールの調整など、現場での連携は成果に直結します。チーム全体で動画活用の目的とゴールを共有することが、展示会成功の鍵となります。また、外部パートナーとの連携もスムーズに行うことで、トラブル防止やクオリティ向上につながります。
今後の展示会動画トレンドと検討すべきポイント
今後は、よりインタラクティブ性や没入感を追求した体験型演出が増えると予想されます。AR/VRやAI技術を組み合わせた双方向コンテンツ、さらにはハイブリッド展示会でのマルチデバイス対応が標準となってくるでしょう。また、サステナビリティや多言語対応、アクセシビリティへの配慮も重要なポイントです。
導入を検討する際は、ブース設計や配信環境、ターゲット層の体験ニーズなどを事前に整理し、動画の汎用性と拡張性を考慮することが重要です。常に新しいトレンドや技術動向をチェックし、自社の展示会戦略に最適な動画活用を検討しましょう。
まとめ
展示会動画は、来場者の注目を集め、短時間で正確に情報を伝え、ブランド体験や営業成果を生む強力なツールです。企画・撮影・編集・活用の各ステップで戦略的に設計し、ブース設計や体験型演出と組み合わせることで、来場者の理解・関心・記憶を最大化できます。
さらに動画を、オンライン配信や営業資料に再利用することで、費用対効果を高めることができます。最新トレンドや映像技術、AI活用を取り入れ、効果的な制作・運用方法を考え、目的やターゲットに合わせた動画を活用することで、展示会での成果を最大化できます。
費用や運用体制、今後の技術動向も踏まえ、PDCAを回すことで、展示会動画は企業のマーケティング資産として長期的に価値を発揮します。効果的な動画制作と活用で、展示会での差別化と成果向上を実現しましょう。
弊社「コンテンツ東京」展示会ブース
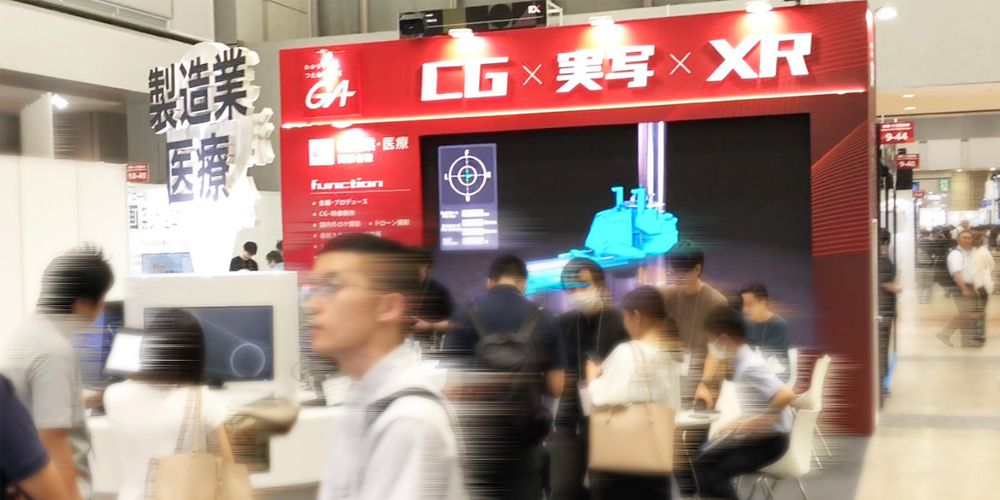
弊社は、企画から撮影、編集、CG制作、キャスティングまで、映像制作に関わるすべての業務にワンストップで対応しています。各工程を自社のスタッフが担当しますので、適正な料金でクオリティの高いプロモーション動画を制作します。その他の動画制作実績も豊富にあるため、動画制作を考えている企業の方は、ぜひ一度お問い合わせ・ご相談ください。